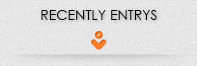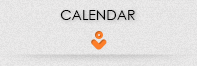おざわやの代表のブログです
朝活で学ぶということを考えてみました
2019.04.22
今日は朝から暖かくて、お昼に向けてグングン気温が上がってきたので、現場監理と軽作業でずっと外にいてバテましたー。
こんばんは、店主のおざわです。
とその前に今朝も毎週月曜日の朝活ネットワーク名古屋へ。 この朝活では特にジャンルは決まっていなくて、主宰の宮崎さんが「面白い!」と思った人の話を聞きます。ある時は会社の社長、またある時は大学生だったり主婦だったり、時にはただの純喫茶好きだったり。とにかく振れ幅がスゴくて、だからこそ「今朝のスピーカーは誰かな?」なんて楽しみにしながら、早起きして会場に向かいます。だって、自分が興味あるとか好きな話ばかり聞いてたら、自分の幅も拡がらないと思いますしね。
今朝はメタファシリテーションを学びました
これまで魅力的なファシリテーターに数多く会ってきました。沢山の人たちが集まった中で、その会が円滑に進むよう場を和ませて全体のゴールを目指すファシリテーションの有効性も見てきました。でも「メタファシリテーション」っていう言葉は知らなかったし、似ているけどそれがどう違うのかにも興味ありました。そこで感じたことを今日のブログに是非書いてみたいと思いました。
相手のneedsではなくwantに気づいてもらう対話、メタファシリテーションの手法と実例を聴きました。
「なぜ?」を聞くと感情や意見が出てきて「事実」に行き着けないってこと、問題解決の場じゃなくても大切だと思いました。初めは難しいけど、クセにすれば考えなくてもできるそうです。#今日の朝活 pic.twitter.com/5EP4a4xdCE— おざわあつし お墓まいりの楽しさを伝える石屋さん (@stone_ozawaya) 2019年4月22日
今日のスピーカーは開発途上国での課題を解決するために年に数回は海外に行くという松浦史典さんでした。例えば汚れた水を飲むことで死んでしまう子供たちが多い地域に井戸を掘った後、次に行ってもやっぱり子供の死亡率は変わらなかったそうです。それはなぜかと言えば、住民の皆さんにとって子供が死ぬのはごく当たり前のことと思っていたので、あえて井戸を使うよりも今まで通りの池や川の水を飲んでいたからだそうです。
つまりこちらが問題だと思っていることが相手にとっての問題になってはいなかったと。それを解決した手法がメタファシリテーションだったんです。
なぜ?と聞かずになぜそうなっているのかに「気づかせる」のが目標
例えば仕事や学校などで遅刻した事って誰にでもありますよね。そんな時に「なんで遅刻したの?」と聞かれたらどう答えますか?寝坊したとか電車に乗り遅れたとか、要するに「言い訳」しますよね。なぜかと言えば、それはそういう答えを求める質問だったから。なのに「言い訳するな!」なんて言われても困りますよね。ならばどうするかと言えば、誰に聞いても変わりようのない「事実」のみを質問すること。そしてその事実の積み重ねから、何が問題なのかを「相手に」気づいてもらうことが大切だそうです。
「何時に起きたの?」「昨日は何時に寝た?」「ここに向かう前は何してた?」などと聞けば、嘘をつかない限りは事実しか答えようがないですよね。大事なのはそんな質問の中から本当の問題がどこにあったのかを伝える訳でもなく、相手が気付いてくれるまで辛抱強く待つことだそうです。
問題解決の場だけじゃなく普段の生活の中でも大切なこと
これは途上国での問題解決の場などに限られた事じゃなくて、ごく普通の職場や家庭などでも大切な事じゃないかなって。それぞれの感情や意見に囚われてしまい、本当の問題から離れてしまって紛糾してしまう事もよくありますよね。これはどんな場合にも起こりえることだから、普段から意識していれば周りとの関係が改善するんじゃないかと思いますし、そもそも相手に何かを「伝える」ということにも繋がるんじゃないかと。
朝活が終わってから直接松尾さんに「質問の順番などで相手に与えるイメージが変わっちゃわないですか?」と聞いてみると、「確かにそうですが、慣れだと思いますよ」と。なんなら家族や友人との会話の中からも練習すれば、どんどん慣れるしコツが掴めますと聞いて、ぜひ意識してやってみようと思いました。
そんな出会いを作っていただける場が大切なんです
今日の学びに限らずこれまでも沢山の出会いや学びをいただいているこの朝活は、もはや生活の一部になりつつあるような気もしています。というわけで今日はメタファシリテーションについて書こうと思っていましたが、実はボクの中での「今日の課題」は朝活での学びにありましたというブログになりました。
そしてそんな朝活ネットワーク名古屋は先週で通算300回を超えたってことで、明日の晩は「夜活ネットワーク名古屋」としてお祝いの飲み会。それもまた気づきの元になるかも?いや、ただ楽しく飲むだけでも良いですよね。
そんな期待感と共に今日のブログはこんなトコで!